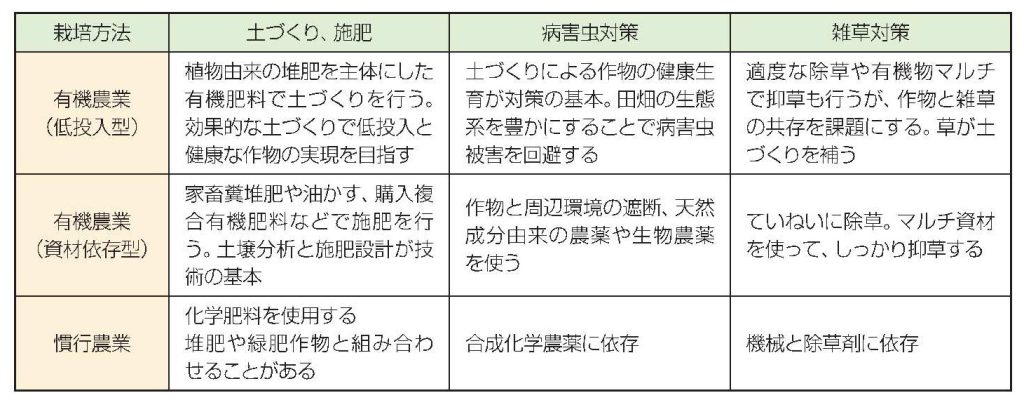土づくりの基本
健康な土とは
生命力豊かな健康な土が、栄養豊富で健康な作物を育てます。有機農業では、堆肥や有機肥料は作物の食べものではなく、「土を育てる土の食べもの」です。この考え方にもとづく実践では、「作付けごとに施肥しなければならない」という固定観念から解放されます。
1作ごとに作物の吸収量を見計らい計算しながら施肥量を決める栽培法がある一方で、年に一度の適量の堆肥施用ですべての作物に対応させる栽培法も成立します。これは、よくできた土が作物にちょうどよい質と量の養分をもたらしてくれるからです。このように、作物がうまく育つように見守ってくれる土を養うのが土づくりです。
土づくりは、①農地土壌に有機物を供給することから始まります。投入された有機物を餌にして、②ミミズや微生物などの土壌生物を活性化させ、そのはたらきを高めます。その結果として、③土壌の団粒構造が発達し、栄養地力(肥料効果)が高まり、併せて病害虫抑制効果、土の中の環境を安定させる効果などが向上します。
この土づくりがうまくいけば、①生産が安定して冷害や干ばつなど気候変動の影響を受けにくくなり、②病虫害を受けにくくなり、③農産物の栄養価が高まり、味が濃くなり、日持ち性もよくなる可能性が出てくるほか、④土壌侵食の防止になり、そして⑤周辺の生態系を守るスタート地点になります。
土づくりに用いる有機物
土づくりに使う有機物には、さまざまなものがあります。まず利用してほしいのは、地域の有機物資源です。山林・雑木林などの落ち葉や田畑周辺の刈り草など天然資源、家畜糞尿、イネやムギのワラ・モミガラ・米ぬかなどの農業副産物、生ごみや食品加工時の余りものなどです。河川や海に近いところであれば、貝殻や海藻くず、魚加工残渣など水産業の副産物も有効です。地域の消費者や他産業との連携が重要な課題になります。
こうして入手した有機物を十分に発酵腐熟させて、質のよい堆肥や発酵肥料にして施します。既存の堆肥や有機肥料を他から購入するだけでなく、自作できる技術が、有機農業の基本要件です。研修中に、堆肥やボカシ肥料の作り方を体験的に学ぶ機会があるとよいでしょう。
有機物の施用で大切なのは、必要以上に入れすぎないことです。とくに、家畜糞堆肥の使い方は慎重に行います。土の許容量以上に入れると、不健康な生育になってさまざまな問題の引き金になるからです。
土づくりは焦りが禁物。少し足りない程度が生きものの活発なはたらきを促し、作物も健やかに育つ傾向があります。低投入安定型の作物栽培が、21世紀の有機農業の潮流です。研修では、たとえば有機物量の加減と病害虫の発生のしかた、生産物の美味しさなどを試しながら、研究心を育てましょう。
緑肥作物の活用と耕し方
土づくりのために、農地で有機物を育てる方法もあります。ムギ類やマメ科牧草種などを畑で育てて土にすき込む、緑肥作物の利用です。この応用で、害虫の忌避や天敵の呼び寄せに用いたり、雑草を抑えたりするために利用するなど、用途はどんどん広がっています。
また近年は、耕し方の工夫が有機農業の新しい課題になっています。できるだけ耕さない耕作法が土の中の生きものを守りやすく、低投入に近づきやすいのです。緑肥草生法、機械の使い方、耕す時期の検討など、次代を担う若い研修生に新しい技術や課題を意識させましょう。
文/涌井 義郎
ガイドブック「有機農業をはじめよう!研修生を受け入れるために」8-9ページ
「有機農業の考え方」6-7ページ、「作付計画」10ページも参照ください。